秋の七草フジバカマをとりまく神秘

本ページにはプロモーションが含まれています。
フジバカマ(藤袴)について
フジバカマ(学名:Eupatorium japonicum)は、キク科ヒヨドリバナ属の多年草で、日本、中国、朝鮮半島に分布しています。秋の七草の一つとしても知られ、古くから日本で親しまれてきた植物です。
特徴
◇ 花
開花時期:8月~10月
淡い紫色やピンクがかった白色の小さな花が集まって咲く
花には甘い香りがあり、乾燥させると桜餅のような香りがする
◇ 葉・茎
茎は直立し、高さ1~1.5m程度に成長
葉は対生(向かい合って生える)し、3つに裂けた形をしている
乾燥させると特有の香りがある
生育環境
日当たり:日向または半日陰を好む
土壌:湿り気のある肥沃な土地が適している
耐寒性:比較的強いが、強い乾燥には弱い
フジバカマとアサギマダラ
フジバカマは蝶の「アサギマダラ」が好む蜜源植物としても有名です。アサギマダラは長距離を移動する渡り蝶であり、秋になると日本各地でフジバカマの蜜を吸う姿が観察されます。
フジバカマ(学名:Eupatorium japonicum)は、キク科ヒヨドリバナ属の多年草で、日本、中国、朝鮮半島に分布しています。秋の七草の一つとしても知られ、古くから日本で親しまれてきた植物です。
茎は直立し、高さ1~1.5m程度に成長
葉は対生(向かい合って生える)し、3つに裂けた形をしている
乾燥させると特有の香りがある
栽培方法
植え方
春(3~5月)または秋(9~10月)に苗を植える
株間は30~40cmほど空ける
水やり
乾燥しすぎないように、土が乾いたら適宜水を与える
剪定・管理
花後に剪定し、枯れた茎を整理すると株が元気に育つ
繁殖力が強いため、増えすぎたら間引く
フジバカマの歴史・文化
平安時代から香りを楽しむ草として使われ、「源氏物語」にも登場する
乾燥させて匂い袋や防虫剤として利用された
近年では自生地が減少し、絶滅危惧種に指定される地域もある
フジバカマは、日本の秋を彩る風情ある植物であり、香りや蝶との関わりなど、さまざまな魅力を持っています。育てやすいので、庭や鉢植えで楽しむのもおすすめです!
アサギマダラの研究・調査
アサギマダラの研究や調査を行っている主な団体をご紹介します。
アサギマダラの会
青い大空を高く飛び、海を渡って移動するアサギマダラは、謎の多い渡りチョウです。その生活は、マーキング調査により、少しずつ明らかになってきました。日本から台湾、中国南部、香港まで飛んだアサギマダラもいます。あなたも一緒に旅をするアサギマダラの謎を追求しませんか。あさぎオーグ
旅をするチョウ・アサギマダラのあらゆる情報が入手できます。
アサギマダラの会では、油性黒色フェルトペンで、羽の白っぽい部分に英数字のマークをつけて放すマーキング調査を行っています。再捕獲されると、移動の実態がわかります。
最近では1年間に約10万頭のアサギマダラにマークがつけられ、約2000頭が再捕獲されています。あさぎオーグ+3あさぎオーグ+3とやまマップ+3
入会すると、旅をするチョウ・アサギマダラのあらゆる情報が入手できます。連絡誌「We love! アサギマダラ 情報」が年2回以上、学術誌「Parantica」(パランティカ)が年1回以上届きます。また、アサギマダラなどの移動昆虫のメーリングリスト「asagimadara」にメールアドレスが優先的に登録されます。omu.ac.jp+4あさぎオーグ+4あさぎオーグ+4
マーキング会、調査会、まとめの会に参加することで、マーキングを楽しみながら、充実した人生を過ごせます。家族の1人が会員になれば、家族の全員が会員扱いですので、一家そろってマーキング会に参加して、自然体験ができます。
マーキング会は全国で行われ、その情報もメーリングリストなどで入手できます。あさぎオーグ+1あさぎオーグ+1
アサギマダラの誘引植物や、食草を庭に植えれば、ご自宅の庭でマーキングができます。あさぎオーグ
アサギマダラに興味があれば、ご入会ください。あさぎオーグ
富山アサギマダラ調査グループ
富山県自然博物園ねいの里では、2002年より、富山アサギマダラ調査グループを立ち上げ、旅をするチョウ『アサギマダラ』の移動解明に取り組んでいます。
アサギマダラは、薄い水色の斑模様のある翅をもつ蝶で、夏から秋にかけて富山県内(特に山地)で舞っているのを見かけます。春は、台湾や沖縄など南方から北上移動してやってきます。8月以降、涼しくなってくると、南下をはじめることがわかっています。とやまマップ+1ces-net.jp+1
調査グループの活動として、マーキング方法はどなたでも参加できる簡単な作業です。捕獲したアサギマダラの翅に与えられた標識番号を記入し、調査書に必要事項を記録します。
捕獲場所・日時・性別・状況を定められた記入用紙に記入し、事務局に報告します。その後、標識番号と記録書を確認し、その場で放蝶します。とやまマップ
富山アサギマダラ調査グループでは、調査を開始した2002年から、毎年40個体以上のアサギマダラの移動を確認しています。
調査員を募集しており、初心者歓迎で、アサギマダラに標識をつけてみたい、興味のある方はグループ事務局へご連絡ください。とやまマップ
その他の研究活動
玉川大学大学院の研究グループは、アサギマダラの雄がヒヨドリバナやフジバカマなどの花から「ピロリジジンアルカロイド」という成分を摂取し、性フェロモンの原料や交尾行動を活性化させる物質として利用していることを発見しました。
このような習性は「薬物食性」と呼ばれ、薬物によって行動が活性化されるという例はアサギマダラの雄で初めて発見されました。玉川大学+1あさぎオーグ+1
また、社会福祉法人 湖成会では、柚野中学校の生徒や地域の方々と協力して、アサギマダラが好むフジバカマを植える「アサギマダラプロジェクト」を始動しています。

これは、地域にアサギマダラを呼び寄せるための取り組みであり、地域の自然環境保全にも寄与しています。佐賀県厚生会
これらの団体やプロジェクトは、アサギマダラの生態解明や保全活動に取り組んでいます。興味のある方は、各団体のウェブサイトをご覧になり、参加をご検討ください。
アサギマダラの研究者
泉田啓氏:京都大学の教授で、アサギマダラなどの蝶の飛翔メカニズムを研究し、超小型飛行機の実現に向けた研究を行っています。
栗田昌裕氏:医学博士でありながら、「一番数多くのアサギマダラに出遭った人」とされるアサギマダラ研究の第一人者です。 PR TIMES
木下充代氏:総合研究大学院大学の准教授で、アサギマダラの季節性ナビゲーションの神経行動学的研究を行っています。 kaken.nii.ac.jp

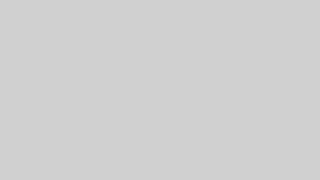
コメント
コメント一覧 (3件)
評価高いです、ホンネレビューが読める。あなたのサイトこそが本物。素晴らしい仕事!。 [url=https://iqvel.com/ja/a/%E3%82%A6%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%8A/%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E4%BF%AE%E9%81%93%E9%99%A2]静寂の祈り[/url] 質高い 実用度高い具体性。
書き方めっちゃ生き生き。心から!で 温かさもらえます。 [url=https://iqvel.com/ja/a/%E3%83%9C%E3%83%AA%E3%83%93%E3%82%A2/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%82%B3]チュキサカ県[/url] 驚きのレベル 誠実・詳細な公開。
だいぶ前に頂いたコメントのようですが、返信が遅れました。ありがとうございます。
小生WordPressなどのシステムに疎く、何をどう書いたらよいのかわかっていないのです。
教えてください。
今後ともよろしく。