本ページにはプロモーションが含まれています。

横浜の三渓園に展示された横浜さくらそう会会員の作品
植え方、管理
1月なかば、2月初めは、正に桜草の植替え時期です。桜草は3月に芽生え4月に花を咲かせ春を謳歌しますが、その後野にある時は雑草に埋もれ溶けるように消えていきます。
鉢植えの場合にも条件の良い場所に置いても葉があるのは7月までで8月にならぬうちに消え始めます。たまに肥しのやりすぎなどから小さい芽が次々に出てくることがあります。これは来年の芽のためにはベストではないでしょう。
桜草は、8月から年明けの2月のまでの7か月は地中で生活しています。ですからその期間中の管理が実は大事で、良い芽はこの時期につくられます。
1~2月は、特に寒いので鉢数を多く持つ人は10月~11月頃から植替えをする人も増えました。この頃から植え替えても生育に問題はなさそうです。
しかし花の高さをそろえ、5号鉢に4本の苗を形よく収める江戸伝統の美形に仕上げるには、開花期近くの2月に同じボリュウムの芽を四ツそろえたほうがうまくゆくようです。
鉢の大きさの1号は約3㎝、5号は直径約15㎝です。

用土は、あまりこだわりません。市販の草花用の培養土でもだいじょうぶですが、赤玉小粒7、培養土3、くらいが基本です。中粒を使う人もいます。
いろいろ工夫して用土を作るのも楽しみになります。鉢によっては底石が必要です。最近使用する人の増えたプラスチック製の「陶鉢」(スエバチ)などでは必要ないかもしれません。底が網状になっているからです。
鉢の半分ほどに用土を入れ、苗を4ッ寝かして置きます。ひげ根がからみあって狭苦しく感じるかもしれませんが、桜草はもともと群生していて根が密生していますからそれが自然なのです。 根の中央に白くとがった芽があります。その上に1㎝ほど土を乗せ株全体では2㎝くらい被せれば植替えは終わりです。
近年東京近郊では、30年前に比べ暖冬になったため改めて霜除けをしないようになりました。しかし赤玉土は霜柱が立ちやすくうっかりすると株全体が地表に持ち上げられてしまいます。それなりの対策は必要でしょう
霜で花芽が少し地表に出てしまったくらいでしたら指先で軽く押し戻してやれば大丈夫です。
桜草全体としては、寒さに強く植替えしない鉢がカチカチに凍っても問題ありません。また年間を通じて大切なのは水やりです。赤玉土、腐葉土での栽培ならば水をやり過ぎて根腐れすることはまずありませんから水を切らさぬよう十分与えましょう。桜草は、夏の高温下の乾燥がとくに苦手です。
夏になると自然に葉がなくなります。葉のなくなった鉢の水やりはとかく忘れがちです。有注意です。江戸時代には桜草用の鉢がなく台所用品だった陶器の底に穴をあけて使っていました。「孫半斗鉢」と呼ばれ今では骨とう品扱いの高値になっています。
それに似せて作った陶器鉢も沢山ありますが「陶鉢」(スエバチ)というプラスチック鉢が意外に見栄えもよく苗の生育にもあっています。

左からプラスチック製の(「陶鉢」スエバチ)中央丹波焼、右土管鉢呼ばれる桜草鉢
肥料 液肥(ハイポネックス1000倍)を10日おきくらいの感覚で5月末まで与えます。それ以外のものはどういう感じの花を目指すのかいうこととの相談になります。

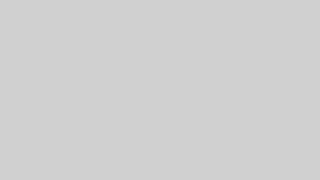
コメント